フランス欧州ビジネスニュース2025年10月9日(フリー)
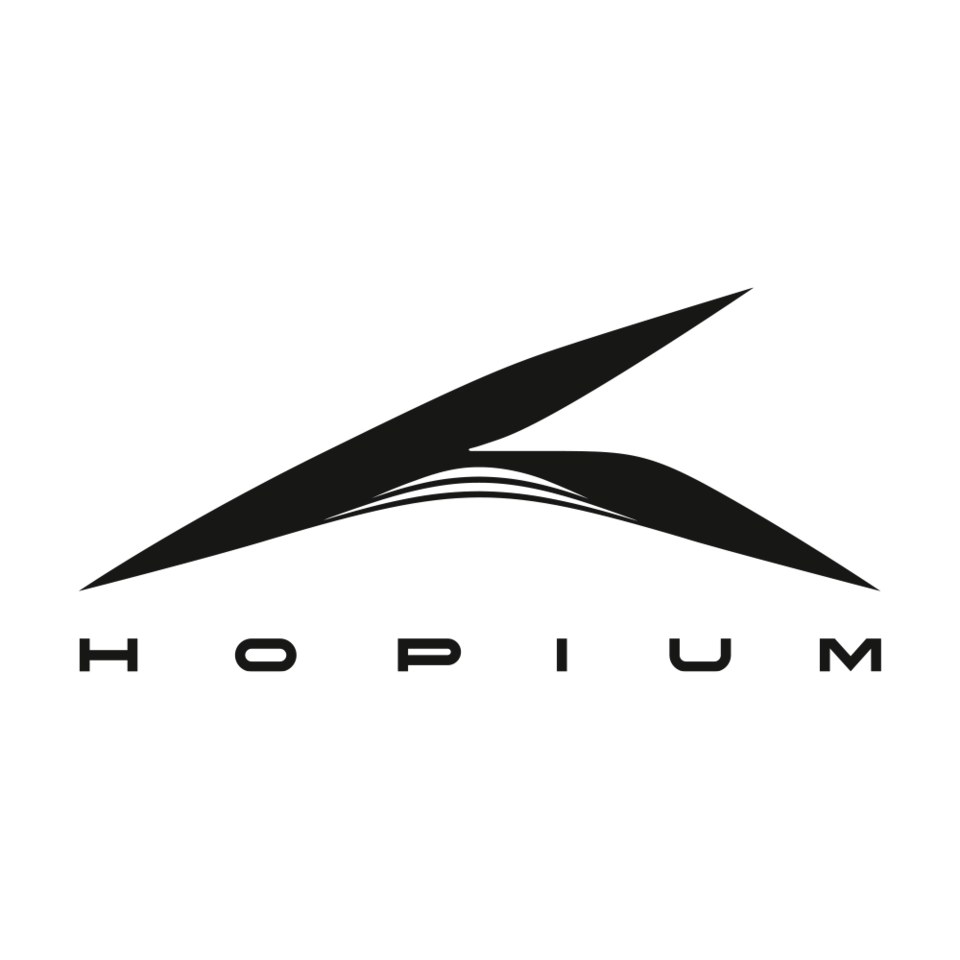
1. 「レトリックはもう十分だ」IMF 、欧州に対し、競争力向上に向けた行動促す
2. CO2:バイオ燃料が化石燃料よりも悪いと推定している衝撃的な報告書
3. ヨーロッパのリサイクルプラスチック、アジアの競合に遅れをとる
4. ソフトバンク、スイスABBの産業用ロボットでAI帝国を拡大
5. 欧州のベンチャーキャピタルの常識を覆すファンド「Plural」
6. タレス、量子脅威に対抗できるよう設計されたスマートカードを発売
7. フランス国家情報システムセキュリティ庁Anssi、2030年以降、量子コンピュータセキュリティ対策が施されていない製品を購入することは不可能に
8. ヴァレオに倣い、中国の希土類を使わずに事業を展開している企業
9. 水素自動車の失敗後、ホピウム、海上および定置型エネルギーにピボット
10. 制御可能で、収益性が高い...地熱エネルギーが将来の再生可能エネルギーになったらどうなるか?
1. 「レトリックはもう十分だ」IMF 、欧州に対し、競争力向上に向けた行動促す
IMFのクリスタリナ・ゲオルギエワ専務理事が、欧州の競争力低下に警鐘を鳴らし、空疎な議論ではなく実行を促している。ワシントンでの講演で、労働・財・サービス・エネルギー・金融に残る越境フリクションを除去し、「単一市場のツァー」に実権を持たせること、欧州単一の金融システムとエネルギー同盟の構築、そして米国民間部門のダイナミズムに追随することを提案した。象徴として、創業から51年以内の米メガ企業7社の時価総額が同年齢の欧州企業群を凌駕している点を挙げている。これは9月16日にマリオ・ドラギが示した「このままでは欧州は世界経済地図から消える」との警告をなぞるものでもある。マクロ見通しでは、世界経済は2025–2026年に小幅減速にとどまり、中期の成長率は約3%(パンデミック前の3.7%を下回る)としている。米国の関税引き上げは大規模報復が乏しく、世界は「貿易戦争」を回避している一方、企業はサプライチェーン再編で適応している。だが不穏な兆候もある。金の需要が急増し、金準備が世界の公式外貨準備の20%超に拡大。関税の完全な波及は未確定で、米国では企業マージン圧縮→価格転嫁→インフレ再燃の恐れがあり、FRBの利上げリスクも示唆される。中国の輸出振替は各国の関税引き上げ連鎖を招き得て、EUも中国鉄鋼に対する関税を2倍にする方針を示した。世界の公的債務/GDPは2029年に100%超へ向かう見込みで、失業と生活不安は若者の抗議拡大として表出している。求められる処方箋は、米国が民間貯蓄促進と財政赤字縮小(戦後最高の106%に迫る債務比率)へ、中国が民間消費を押し上げる財政パッケージへ、そして欧州が単一市場の統合加速と規制・投資の実行へ舵を切ることである。
2. CO2:バイオ燃料が化石燃料よりも悪いと推定している衝撃的な報告書
ロビイング団体T&Eが公表した報告書は、現行のバイオ燃料がライフサイクル全体でCO2を化石燃料比+ 16%排出していると結論づけている。根拠はCerulogyの分析と世界銀行データで、トウモロコシやサトウキビなど1次世代原料への依存が大きく、ブラジルやインドネシアの強い農地拡張と森林破壊が平均排出を押し上げているためである。こうした地域では排出が化石燃料の2〜3倍に達し得る一方、欧州や米国では削減効果が残るとする。現在、燃料需要のわずか4%に過ぎないバイオ燃料のために約 3,200万ヘクタール(イタリア相当)の農地が使われており、需要が2030年までに40%増えると、農地は60%増の約 5,200万ヘクタール(フランス規模)に拡大、世界の耕地面積で6位相当になる見込みである。T&Eはこれは「巨大な土地の浪費」だとし、その3%に太陽光を敷設すれば同等のエネルギーを賄え、電気自動車約4億台(世界保有台数の1/3)を走らせ得ると試算する。資源負荷でも、100km走行あたりの水使用はバイオ燃料が約3,000リットル、太陽光由来の電力は約20リットルにとどまるという。もっとも将来需要は規制やEV普及に左右され、廃棄物や使用済み食用油などを原料とする2次世代バイオ燃料や合成燃料の拡大余地はあるが、政策と供給力が追いつかず、2030年時点でもバイオ燃料需要の約90%を食料・飼料作物由来が占めると見込む。報告書は、脱炭素の整合性確保には土地利用と供給地構成の是正が不可欠であると警告している。
3. ヨーロッパのリサイクルプラスチック、アジアの競合に遅れをとる
欧州のプラスチック産業が競争力を急速に失っている。再生プラスチックの生産は、欧州(EU27+英・ノルウェー・スイス)が7.8百万トンで3年横ばいの一方、中国は2024年に12.5百万トン(+ 45%)へ拡大し、世界シェアは欧州19.1%、中国30.3%、アジアその他が24.6%となっている。世界の再生材は初めて総生産の10%超に達したが、伸びを牽引しているのはアジアである。欧州主導だったケミカルリサイクルでも、アジアと米国(IRAの後押し)が台頭している。欧州の25%再生材義務(飲料ボトル)を梃子に中国製PETが流入し、価格は平均30%安、大手の中には調達の4分の3をアジアに依存する例もある。一方で「再生」表示の一部がバージン材との疑義も出ているが、欧州停滞の主因ではない。現場では仏で機械式リサイクル4拠点閉鎖、ケミカル2案件中止が発生し、欧州全体で100万トン(設備の 8%)の能力が閉鎖過程にある。2017年以降に50〜60億ユーロ投じ能力倍増を図ってきただけに、需要不確実性が投資を揺るがしている。基礎化学でも欧州のナフサ・ガス・電力コスト劣位が深刻で、生産は62.3→54.6百万トン(2018–2024)へ減少、貿易量は赤字化した。輸入源は中国に加え米国が原料で首位となり、関税も米国材6.5%→0%に下げられる一方、欧州材は 15%課税の非対称が続く。基盤設備のスチームクラッカーは既に7%が閉鎖・閉鎖中で40%が脅威下にあり、サプライ全体に波及している。業界は電力多消費型への支援、安定的規制枠組みとより高い再生材義務、化学・プラスチック貿易の監視機関、および対称的な関税をブリュッセルに要請しており、迅速な政策対応がなければ欧州の高付加価値分野まで侵食されるリスクが高まっている。
